ミッドフィルダーの底、ディフェンダーの前に位置するのがボランチです。
そのボランチはサッカーにおいて重要なポジションになります。
そこを見るだけでチームのやりたいことがわかると言われるほどです。
ボランチの人数や役割によってチームの戦術も変わるからです。
なので、今回はそんなボランチについて、役割や必要な能力などを
詳しく解説していきたいと思います。
☑ 本記事の内容
- ボランチの役割がわかる
- ボランチに必要な能力がわかる
この記事はボランチのことを知りたい人向けになっています。
では早速解説をしていきますね。
ボランチとは?定義について解説
そもそもボランチとはどんなポジションなのかを説明していきます。
ボランチとは中盤(ミッドフィルダー)の底、攻撃的なミッドフィルダーとDFの間にいる選手のことです。
「ボランチ」の語源は、ポルトガル語の「舵取り」から由来していると言われています。
その名の通り、チームの土台となるようなポジションです。
攻撃のときはパス回しの中心になったり、守備のときは味方の動きをサポートしたりします。
攻守でバランスを取る難しいポジションです。
日本で「ボランチ」という言葉が定着したのは、90年代の後半と言われています。
しかし、日本の場合は「操縦する」と言う意味よりも、中盤の底にいる人=ボランチと言う意味で使われることが多いです。
役割というよりは、中盤のポジションをわかりやすく分けたときの名称という意味合いが強いと思います。
国によってはボランチの役割ごとに名前がありますが、今回は全て「ボランチ」で話します。
ボランチの役割について解説
・相手をゴールに近づかせないようにボールを取る
・ゲームを読み適切な場所に行くこと
ボランチの役割は大まかに上の3つです。
攻撃にも守備にも貢献しなければならない難しいポジションと言えます。
この役割のどこに比重を置くかによって選手選考や戦術が変わっていきます。
簡単に言えば、攻撃的な選手か守備的な選手かもしくはバランサーを置くかです。
そんな役割について解説をしていきます。
ボランチの役割①:パスを供給することで味方のチャンスをつくる
ボランチの役割はパスをつないで攻撃の起点になることです。
中盤の底は前のポジションに比べて、相手の圧力が比較的緩いので、ボールを持ちやすい特徴があります。
なので攻撃のチャンスを多く作ることが可能です。
ロングボールやショートパスを駆使してゲームを支配していきます。
この役目を担う選手は、そのキック精度を信頼されていることがほとんどです。
比較的守ることが苦手でも展開力があれば任されます。
パスを使って状況を打開するのがボランチの役目です。
ボランチの役割②:相手をゴールに近づかせないようにボールを取る
ボランチの役割2つ目はボールを取る、いわゆる守備です。
中盤の底はボールが集まりやすいポジションになります。
ボランチの後ろとセンターバックの前の空間を上手く使うとゴールが生まれやすいからです。
なのでそのスペースを使わせないように守備ができるのが求められます。
そこをちゃんと守れると、そう簡単にゴールを奪われることはありません。
攻撃の選手とは逆に守るのが上手い選手を使ってどんどんボールを奪ってカウンターに持ち込みます。
なので、体が大きい選手やボールを取るのが上手い選手が担当することが多いです。
豊富な運動量とボール奪取で、素早く前線にパスを送ってチャンスを作ります。
最近ではセンターバックをこのポジションに配置するチームも出てきています。
守備力がありながら、ビルドアップをするためにパスも出せるので、もってこいかもしれません。
どちらもできる選手もいるので、そういった選手を並べるのが一番です。
でも、短所以上に長所があるなら、補いながら組むことで1+1が3にも4にもなります。
ボランチの役割③:ゲームを読み適切な場所に行くこと
ボランチの役目の最後は適切な場所に動いて、味方を助けることです。
ボランチは真ん中にいることが多いので全体のバランス役を担います。
そうすることでチーム全体の配置が崩れにくくなるからです。
例えば相手が左から攻めてきた場合、守りは左寄りによります。
でも、全員が左に行けば、右が空いてしまうリスクが高いですよね。
それを避けるためにボランチを見ながら適切な距離をとってリスクを分担します。
チーム全体のバランスを取る役割がボランチです。
味方の攻守のフォローもするので、パスをもらえる位置やボールがきそうな位置を把握することも求められます。
頭が良くないと難しいポジションといえます。
ボランチの役目は大きくはこの3つです。
タイプによって得意なプレーも違います。
・守備的な選手の役割は、ボールを取ること
ボランチの配置によって役割が変わる?!
・ボランチが2人の場合
ボランチの役割について話してきましたが、フォーメーションの人数によっても役割が変わってきます。
何人配置されるのかによって役割が変わるからです。
そのことについてこれから解説していきますね。
ボランチが1人の場合
中盤のそこに1人だけを配置する場合です。
ワンボランチとも言います。
このワンボランチの役割は基本的に真ん中にいることです。
全体のバランスを取るのが役目になります。
自分が真ん中から動かなければ、味方はバランスを取りやすくなります。
1人で中盤の底を全てカバーするので、広い視野とポジショニングが必要です。
でも実際に全てをカバーするのは難しいので、ボランチの前にいる2人と協力して3人でトライアングルを作りながら守ります。
前のミッドフィルダーとの連携が不可欠です。
ワンボランチは戦術によって配置するタイプが変わります。
展開力が売りの攻撃的な選手

攻撃的な選手を配置する場合は守備力よりも展開力が求めまれます。
パスを使って攻撃に厚みを加えるのが役割です。
パス回しの柱として前線にタイミングよくパスを送ることで、得点のチャンスを作ります。
ワンボランチで思いつくのがバルセロナのブスケツです。
攻撃的な志向を好むチームのワンボランチで、パスを武器にゲームを作ります。
パスサッカーを目指すなら注目したい選手です。
守備的な選手

守備的な選手を配置する場合はDFラインの前で壁としての機能を求められます。
センターバックの前に君臨して相手の攻撃を止めるのが役割です。
攻撃よりも相手を確実に止めて、素早くカウンターに持ち込みます。
この守備専用のプレータイプはボランチではなくアンカーと呼ばれることもあります。
アンカーはボールに寄せる力やピッチの中央でどっしりと構えられる安定感が必要です。
守備的な選手でも前のポジションや後ろのポジションとのバランスが大切になってきます。
守備的なタイプでは、レアル・マドリードのカゼミーロです。
中盤の門番として、どっしりと構えながら守備を安定させます。
このようにチーム戦術が違うだけで、異なるタイプが配置されるのが1ボランチの特徴です。
どのタイプが配置されてもバランスを取れる位置取りが大切になってきます。
ボランチが2人の場合
中盤の底に選手を2人並べる場合です。
2人いるのでダブルボランチとも言われます。
2人を並べることでDFラインの前のスペースを埋めることが目的です。
1人では広大なスペースを埋めるのが難しいので、そこを2人で埋めます。
ダブルボランチは2人の距離感が大切です。
1人がボールサイドに出て、もう1人がバランスを取るのが基本になります。
良くあるのが片方が攻撃的な選手で、もう片方が守備的選手の組み合わせです。
ちなみにブラジルでは守備的な方を第一、攻撃的な方を第二と呼びます。
攻撃的な選手は守備が苦手な場合が多いので、守備力が売りの選手がカバーをして、お互いを補完しあう関係が理想です。

ダブルボランチで有名なのが、ピルロとガットゥーゾの組み合わせです。
攻撃的なピルロと守備的なガットゥーゾは、お互いを補完しあい理想的な関係を作り上げました。
このように苦手なポイントを補うことがボランチを2人並べることのメリットです。
ボランチは攻撃と守備、どちらも必要な大切なポジションです。
なので必要な能力もたくさんあります。
次はそんなボランチに必要な能力を解説していきますね。
ボランチに必要な能力を解説
・ポジショニング
・守備能力
・ゲームメイク
・コーチング
ボランチに必要な能力はチームごとに違います。
ですが、これはあった方が良いというのが上記の5つです。
これが全てできればいいですが、苦手な人はそれが得意な選手とお互いを補うことでカバーできます。
なので、得意なところを伸ばすのも一つの方法です。
では順に説明していきます。
ボランチに必要な能力①:判断能力
ボランチに一番必要なのは判断能力です。
どのタイミングでパスをもらい、どのタイミングでパスを出すのか。
攻撃参加はどのタイミングか。守るときはいつ相手に寄せるか。
そうした判断を咄嗟にできなければなりません。
判断を間違えるとチームのピンチを招くことになります。
なので1歩先、2歩先を読める展開力が必要です。
この展開力は試合の中で覚えるか、プロの試合を観ながら自分ならどのタイミングでパスを出すのかを考えていくのが良いと思います。
ボランチに必要な能力②:ポジショニング
ボランチは試合中、自分の位置を考えてプレーする必要があります。
基本は真ん中です。
とはいえずっと真ん中にいれば良いわけではありません。
ここで言うピッチの真ん中とは、サイドの選手、FW、CBそれらの選手のいる位置を結んだ中心にいることです。
ボランチが真ん中を意識してポジショニングをすることで、
サイドやDFラインとの距離感を保つことができます。
もし勝手に動き回られたら、他の選手がカバーに入らなければならなくなるので、マークのズレがおこります。
真ん中にいることのメリットは守備面だけではありません。
ボールを奪ったあとの展開を考えても真ん中にいることがメリットです。
真ん中にいれば、360度どこでもパスが出せます。
ポジショニングを学ぶならプロの試合を観るのが1番です。
ボランチに必要な能力③:守備能力
ボランチに必要なのが守備能力です。
ボランチでボールを奪えたり、相手の攻撃を遅らせることができればピンチは防げます。
そのためには必要最低限の守備能力が必要です。
守備の方法はセンターバックとは違います。
最終ラインではないので、遅らせたり、積極的に取りに行くことなどバランスをとることが大切です。
タイプごとに守り方が変わります。
守備が持ち味の選手は積極的に取りに行きますが、
守備が苦手な選手は、カバーリングをして味方を支えます。
自分に合った守り方をしましょう。
守備が苦手でも場合によっては積極的に守る場面があるので、守れるに越したことはありません。
ボランチの守備もまた実戦や動画を観るのが1番です。
あとは以下の記事を参考にしてみて下さい。
【サッカー】ボランチの守備。相手への距離の詰め方。
【サッカー】ボランチの守備対応。1対1のアプローチ
ボランチに必要な能力④:ゲームメイク
ボランチに必要な攻撃時の能力がゲームメイクです。
中盤の底は比較的プレッシャーがかからないので、ゲームを作るのに最適なポジションといえます。
なので細かいパスや一撃必殺のロングパスなど、一気に状況を変えるゲームメイク能力が求められます。
そのために正確な状況判断と正確に蹴れるキック力が必要です。
守備的な選手でも必要最低限、近距離のパスは正確に出せなければなりません。
攻撃的な選手はそこにロングパスや相手をかわす技術が求められます。
味方選手の動き方に合わせて、正確なパスを成功させる能力が必要です。
日々の練習やDVDを観て蹴り方を覚えていきましょう。
状況判断に関しては実際に試合をして、プロの試合を観るのが学びになります。
ボランチに必要な能力⑤:コーチング
ボランチに必要な能力の最後がコーチングです。
ボランチはフォーメーションの中心にいる選手なので、どこからも均等な位置にいます。
なので指示が出しやすいポジションなのです。
センターバックもコーチングが求められますが、より前の選手に届けることができます。
声や行動力でチームをコントロールするのがボランチの役割です。
コーチングが上手い選手がボランチにいるだけで、前の守備は安定します。
コーチングは日頃から声を出すことやチームメイトとの信頼関係が重要です。
ボランチは注目して見るべきポジションです!!
ボランチの役割や能力について解説してきました。
攻撃的な選手を配置するか守備的な選手を配置するのかによってチームのやりたい戦術はかなり変わります。
ボランチを見れば、そのチームのサッカーがわかると言われるほど大切なポジションです。
攻撃と守備両方が求められ、リーダーシップが必要で、誰でもこなせるポジションではありません。
なので、このポジションにいる選手はいろいろな意味でサッカーが上手いこと多いです。
ぜひ、注目して見てみてください。
もしサッカーを観るならDAZN とスカパー!などがあります。
これを利用してみて下さい。
ということでボランチに必要な役割と能力、技術でした。
他のポジションは以下から見れます。
【サッカー】センターバックに必要な役割と能力、技術。
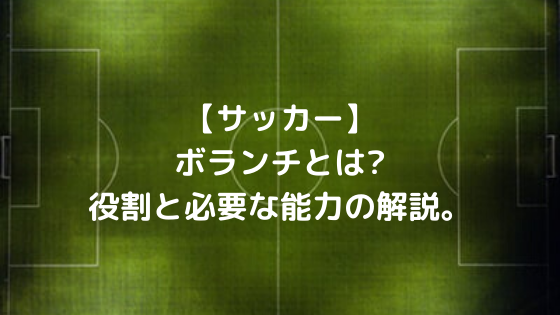
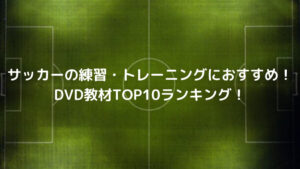
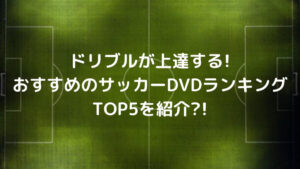
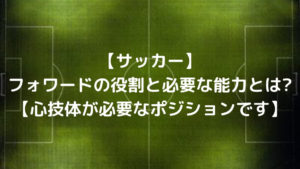
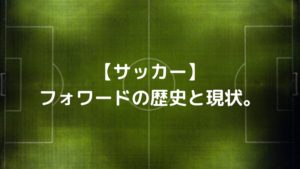
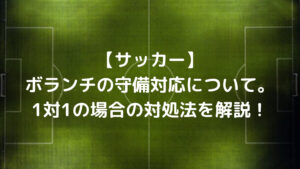
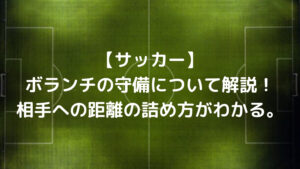
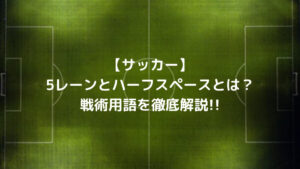
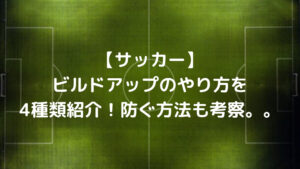
コメント